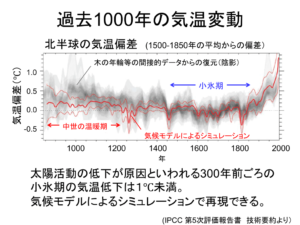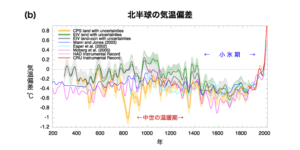最近、郊外や田舎に出かけても、蝶々やトンボを見かけることが少なくなったと感じませんか?
人間の生活と密接な関係にある昆虫たちですが、現在、昆虫の全体の1/3が絶滅危惧種に指定され、個体数が急激に減少しているのです。
最新の研究で、100年後には昆虫のすべてが姿を消してしまう危険性があるという恐ろしい報告が科学誌“Biological Conservation”に発表されています。
とても気になって、報告書の詳しい内容と、昆虫の消えた理由とその影響について調べてみました。
昆虫はあと100年で全滅の危険性!人類の生存にも影響が出る?

この恐ろしいコメントは2019年2月に科学誌“Biological Conservation”に発表された研究報告のヘッドコピーです。
論文の報告者の一人でシドニー大学の環境生物学者フランシスコ・サンチェス・バイヨ先生とその共著者はつぎのように言っています。
昆虫は近年急速に生存の場所を奪われています。
このままでは、10年間で全体の1/4の種がいなくなり、50年で種の半分が消え、100年後には昆虫の姿はすべて地球上から消えてしまうでしょう。
さらに報告は「昆虫たちの減少を止めなければ、地球全体の生態系が壊れて、人類の生存にまで壊滅的な結果をもたらすことになるでしょう」と警鐘を鳴らしています。
世界に昆虫は100万種以上います。
種類の数だけでいえば全生物種の半数以上を占めているのです。
その昆虫の総量がいま1年で2.5%ずつ減少しているという事実から、地球の歴史上6回目の大量絶滅がすでに始まっているのかもしれないといわれています。
昆虫減少の主な理由は・・・
- 農業や都市化が進んで、森林伐採などで生息地を奪われたこと
- 集約型農業に見られる農薬の大量使用による影響
- 森林地帯や特に熱帯地方の気候が変動していること
- 生物学的要因・・侵略種や病原菌による昆虫への影響
・・などです。
このように、気候変動や異常気象も含めて昆虫の減少には、人為的な原因が大きく働いていることが指摘されています。
そして、われわれが食物を手に入れる方法を変えない限り、昆虫は20年から30年で絶滅に向かって突き進んでいってしまうと警告しているのです。
昆虫がいないと食料が生産できない

私達が食料を作るプロセスには虫や動物の協力が必要とされています。
国連食糧農業機関(FAO)によりますと、世界の国の食料の90%を占める100種類以上の食用植物のうち、実に70%以上がミツバチによって受粉しているのです。
世界中の花の咲く植物のほとんどが昆虫たちによって受粉し、繁殖しています。ミツバチや蝶、蛾、ハエ、スズメバチ、甲虫などの昆虫だけではなく、一部の鳥類、哺乳類までが植物の繁殖のプロセスには必要なのです。
食用植物についてもその2/3以上が昆虫の受粉を頼りにして繁殖をしています。
リンゴ、モモ、イチゴ、サクランボ、チョコレートなどの果物はもしもミツバチがいなくなれば、私達が人工で受粉させないと手に入らなくなるのです。

コスタリカのコーヒー栽培の生態系研究で、近くの森に棲息している野生ミツバチのおかげで収穫量を20%増やすことができたという報告があります。ミツバチが姿を消せば、受粉の無料サービス(動物媒)を昆虫が勝手に行ってくれた時代は消え去るのです。自然のすべての花を人工で授粉させることは不可能でしょう。
昆虫がいない世界では生態系は狂い、人類は簡単には食料にありつけなくなるのです。
人間に親しい昆虫が減少して害虫が増える?

この論文は、世界の昆虫の減少について主にヨーロッパと北米大陸の調査報告を精査した結果、特に生息数が減少しているのはチョウとガの仲間だったと報告しています。
イングランドの耕作地では、チョウとガは2000年の始めの10年間で58%、つまり半分以上が消えたという報告まであります。
イギリス、デンマークではミツバチが打撃を受けて個体数を大幅に減らしていること。米国のオクラホマ州で1949年から2013年までに、ミツバチの一種のマルハナバチが半分に減少した事が報告。
このような、ヨーロッパと北アメリカでミツバチのコロニーが消えていく現象“蜂群崩壊症候群”は数年前から英国のテレビやNHKの番組で詳しく報道されています。
さらに、カブトムシやクワガタ、ホタルやカミキリムシなどの甲虫類やトンボ、カゲロウなど子供の大好きな虫たちが、早いペースでその数を減少していると論文は伝えています。
チョウや、ハチなどの大事な昆虫や、動物のふんを処理してメタンの発生を防いでくれているフンコロガシのような益虫まで失いかけているのです。
その一方で、適応力が高く繁殖力の強い、雑食のイエバエやゴキブリなどの害虫が、殺虫剤の抵抗力をつけ、人工の環境に適応して数を増やすだろうと伝えています。
ハチやチョウは花粉を媒介することで植物の生態系に大きく貢献しています。また、他の昆虫や鳥類や動物に補食されて、食物連鎖の重要な一部にもなっているのです。
昆虫が激減すれば、地球の生態系に大きな影響と変化が起きることは間違いないでしょう。
ヨーロッパや北米の各国では、ミツバチの減少や大量失踪には農薬の使用が関係しているとして、その使用を厳しく制限しています。ミツバチの減少の原因は、ハチ自身の栄養状態の悪化や、気候変動による説、農薬による致死説などが指摘されています。
ドイツではネオニコチノイド系の農薬が発売された2006年に、ミツバチの大量死や大量失踪の発生が報告されています。
2007年には、アメリカやネオニコチノイドを空中散布したカナダでミツバチの大量死や失踪が報告されました。
ドイツ、イタリアでは現在ネオニコチノイド系農薬の使用を厳格化しています。フランスでは2018年にフランス議会がネオニコチノイド系の農薬の禁止(2020年には全面禁止)を決めました。
この論文の調査範囲は主にヨーロッパと北米で、日本やアジアは含まれていません。日本の昆虫の棲息状況も同じ傾向にあるのでしょうか。
次の章では、日本でミツバチの様子はどうなっているのかを調べてみました。
日本でも農薬の使用でミツバチが減って、生態系も危険水域?

2009年に長崎県の数カ所でミツバチの大量死が発生し薬害ではないかという報告がされています。また、蜂蜜関連の大手企業・山田養蜂場(本社岡山)にはミツバチを譲ってほしいという話が全国からいっぱい来ていて、対応ができないようです。(公式ホームページ)
日本のミツバチのコロニーも急速に減少しているのです。日本における農薬の規制はどうなっているのか心配です。調べてみましたら、驚いたことに日本ではヨーロッパ各国に比べて規制が大幅に緩やかになっていました。
2024年4月8日に更新されたグリーンピースジャパンの報告“有機農薬ニュース・クリップ”によれば EU各国、米国、カナダ、ブラジルさらに台湾、韓国と比べても大幅に規制が緩やかなことがみてとれます。
過去にさかのぼると、既に、2012年にネオニコチノイドがミツバチにとって致命的だという実験結果が発表されていました。
2012年の9月、金沢大学の自然システム学教授山田俊郎先生は、ミツバチが大量死する“蜂群崩壊症候群(CCD)”にはネオニコチノイドが深く関係していると発表しました。
・・・研究グループの実験の過程を詳しく説明しますと・・・
- カメムシから稲を守るネオニコチノイド農薬2種を水田に散布して、ミツバチへの影響を調べた
- 成長したハチ1万匹の巣箱10個を使用して、2010年7月から1年間、3回に分け野外実験を実施した
- その結果推定されるCCD発生のメカニズムは、外役蜂(外に出て働くハチ)は農薬が散布された場所で即死する
- その不足を補うために内役蜂(巣の中で働くハチ)が外に出てきてその数が減る
- 蜂群の構成(卵、幼虫、内役蜂、外役蜂)が乱れる
- 女王蜂の産卵能力が低下して、コロニーが崩壊する
- 農薬の濃度を低くして外役蜂が即死を免れたとしても、持ち帰った花の蜜や花粉に含まれる農薬が女王蜂や蜂の体内に蓄積して、慢性毒性による障害が出て、コロニーは崩壊する
山田教授は農薬使用を厳格にしないと、日本の生態系に深刻な影響が出ると警告しています。
また、石川県立大学と宮城大学の調査によれば、ネオニコチノイド系殺虫薬を使用した水田ではアキアカネの羽化が従来の30%ほどになったことが指摘されています。
そういえば夏の終わりにやってきて、空にいっぱい舞っていたアキアカネ(赤トンボ)もその数が寂しくなりました。
私達の身近な生態系も危険水域にあるのかもしれませんね。
最後に・・
人は豊かな生活を送るために農業を効率化し、生産性優先の改革を進めてきました。その結果、人類の大事な仲間であるはずの昆虫まで姿を消せば・・いずれわたしたちに手痛いしっぺ返しが飛んでくるかもしれません。
この流れを食い止めるためには世界規模で集中的な努力が必要とされています。今回の論文の報告者の一人でシドニー大学の環境生物学者フランシスコ・サンチェス・バイヨ先生とその共著者は、危険信号を発しながら私達につぎのような提言を発しています。
- 殺虫剤を使わない。
- 有機的な食品を選ぶ。
- 昆虫に優しい畑や、庭造りをする。
だれにでも、すぐにでもはじめられることがいくらでもありますよと言っています。
チョウやトンボがいっぱい舞う日本の原風景がいつか戻って来ますように!
(おわり)
(主な参照記事)
人類のせいで「動植物100万種が絶滅危機」=国連主催会合 – BBCニュース
食料を作るには虫や動物がいなくちゃ! UNP日本語情報サイト
ミツバチとネオニコの研究者が語る、ネオニコ禁止が必要な理由とは
“地球は大丈夫?”のシリーズ記事をご覧くださいね。